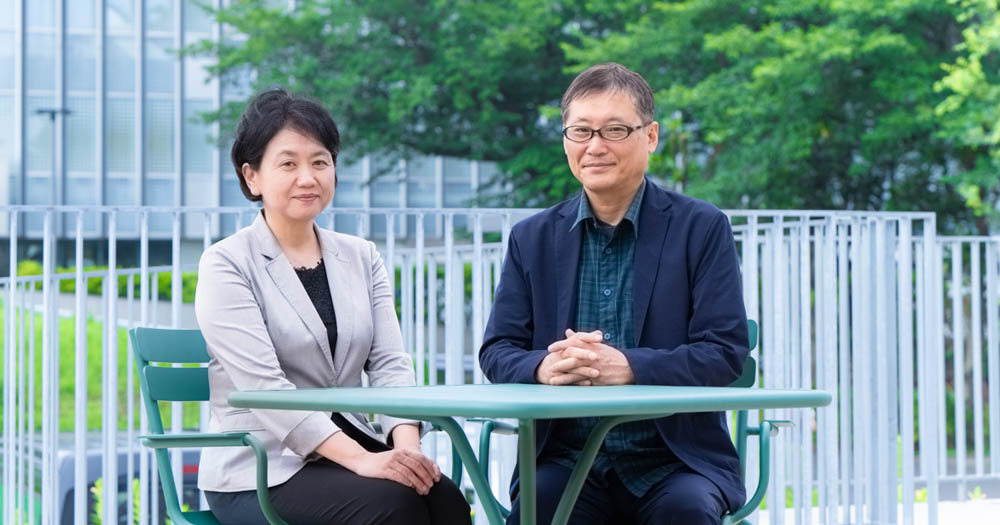講義を通してその企業の魅力が学生に伝わる。
本田さんが担当している「企業と連携したDS・AI教育」とは、どんな内容ですか。
本田 これは大学院の修士・博士課程を対象とした取り組みで、3つのステップがあります。ステップ1が「応用実践系科目」で、現在46社からDS・AIの研究開発の最前線で活躍しているビジネスマンを講師に迎えて講義をしてもらっています。ステップ2は講義に登壇する企業と学生が交流する「DS&AIフォーラム」。そしてステップ3が「インターンシップ科目」で、学生が企業の現場で実際に業務を体験します。
「応用実践系科目」は、DS・AIを活用した社会課題解決に日夜取り組んでいる企業のリアルな話が直に聞けるので、学生に好評です。世に出ている製品やサービスにどのようにDS・AIが活かされているかを知ることができ、触発されるようです。学生にとって「自分の研究のこの部分が応用できるのでは」といったヒントになればと、幅広い業種業態の企業の方を招いて話をしてもらっています。
講義は年間で63コマあり、1社につき1、2コマ、講義だけではなく、最後は課題を提示してもらい、それを受けて学生はDS・AIを活用してどんな解決方法があるか自分なりの答えを出します。企業の側も、学生のフレキシブルな考え方に触れることで新たな活路を見出すこともあるそうです。

学生に人気があるのは、どのような業種・分野ですか。
本田 やはり就活で人気のある企業ですね。特にデータを集めてサービスを提供するIT系企業は人気が高いようです。また電気・電子系や機械系を学ぶ工学院の学生には、メーカー系も人気です。世間であまり知られていない企業でも、学生がこの講義を通してその企業の魅力を知り、就職するケースも増えています。また企業にとっても、東京科学大学にはどんな学生がいるのか、学生の資質を見る機会にもなっています。講義の中で投げかけた質問に対する答えや、課題のレポートなどを見れば、本学の学生の資質がよく見えてくると思います。
企業と学生の交流フォーラム、ナマの声が聞けると大好評。
ステップ2の「DS&AIフォーラム」について教えてください。
本田 優秀な学生を求める企業と学生たちとの交流の場です。幅広い業種の企業の方々との交流を通じて、学生が実社会において活躍する広い視野を得ることを目標としています。
プログラムは、最初に参加企業各社が学生に向けて、自社のDS・AIの取り組みや研究開発内容などをそれぞれプレゼンテーションします。次の「個社セッション」では、学生が関心を持った企業を回って話を聞きます。1社につき15分で、合計4社から話を聞けます。最後は立食パーティー形式の懇親会で、実はこれが学生、企業共に一番評判がいいですね。
スタート時は年1回でしたが、今は年に2回開催しており、約30社がコンスタントに参加しています。参加する企業の数も学生も年々増えていて、手応えを感じています。

ステップ3の「インターンシップ科目」というのは?
本田 企業が主催するインターンシップは一般的ですが、本学では企業にお願いして、DS・AIを使ったインターンシップコースを仕立てていただいています。授業の一環なので、参加して履修した学生には単位を付与します。昨年度から始めて、現在14社で実施しています。
このように本学では3つのステップで企業との「共同教育」を実践しています。企業による講義で応用実践力を身につけ、フォーラムで企業と交流し、インターンシップ型授業で実際に現場を体験するわけです。46社もの企業と連携してDS・AIのエキスパート人材を育成している大学は他にない、と自負しています。
「DS・AIを教える力」も身につけてほしい。
佐藤さんは、先生方の授業を補助するTAの採用などを担当されていますね。詳しく教えてください。
佐藤 一般的には、TAの採用は先生が自分の研究室の学生に依頼することが多いと思うのですが、本機構では「ティーチング・フェロー(TF)育成プログラム」を設け、全学規模でTAを公募しています。これは「DS・AIを教える力」を養うことを主眼としていて、TAの業務を段階的に経験することでポイントが積算され、最終的に「教える力と専門性の両方を備えている」と判定されると、TFとなって授業の一部を担当できるプログラムです。

どのくらい採用しているのですか。
佐藤 年間40名ほど採用しています。学士課程の2年次以降であれば応募できますが、学士課程4年次と大学院課程の学生さんが多いです。大学が「DS・AIを教える力」を客観的に評価するので、学生にとっては就職の際に自分のアピールになります。教えることで自らの学びを深められることも、応募の動機になっていると思います。
TAを継続してTFになった学生は何人くらいいますか。
佐藤 2024年から始まったばかりの制度なのでこれからですが、今年度(2025年度)の後半には初のTFが数名誕生する予定です。彼らには、本機構で開講している科目の授業を一部担当してもらうことを考えています。
学生の優秀さを、企業は驚きをもって見ている。
お二人から見た「東京科学大学の学生」の印象を教えてください。
本田 統合前の東京工業大学の学生に対してであれば、「真面目」「シャイ」「理屈っぽい」、そして「服装のセンスがイマイチ」(笑)というのが、世間一般のイメージではないでしょうか。けれども、近年は大きく変わってきています。それこそ今どきの個性的なスタイルでキャンパスを歩いていて、イケメンもいる。カップルらしき2人が仲良く講義を受けている姿も見かけます。いわゆる女子学生の少なかった東工大時代には考えられなかったことです。
もちろん、頭脳明晰な点は昔も今も変わっていません。応用実践系の講義などでは、たまたま近くに座った4~5人でグループワークを行いますが、即座に打ち解けて課題について熱心に議論しています。後で企業の方から「ここまで高度で斬新な意見をもらえるとは思ってもいなかった」といった驚きの感想をよくいただきます。
佐藤 私は学生さんから履修についての質問を受けることが多いのですが、皆さんとても丁寧でマナーが良いです。メールのやり取りでも相手に気を配った文章が書けています。事務側から「これをやっておいてほしい」と依頼すると、「それが終わったらこうしておけばいいですか。」と、先々のことを含めて考えて行動でき、優秀だなと感じることが多いです。

ぜひ学生に御社の斬新な取り組みについて熱く語っていただきたい。
学生と企業の橋渡しをする立場として、学生や企業の方々へ伝えたいことはありますか。
本田 学生には「先入観にとらわれず、広い視野で社会を見てほしい」と言いたいですね。そのためにも、応用実践系の講義やDS&AIフォーラムにぜひ参加してほしいと思います。応用実践系の講義では、さまざまな企業がDS・AIを活用してどんなことをしているか、具体的な像が見えてきます。またフォーラムに参加した学生からは、「企業の熱量が直に感じられて良かった」といった感想も寄せられています。本学の学生は、各企業から非常に大きな期待を持たれています。それを、声を大にして学生の皆さんに伝えたいですね。
佐藤 そうですね。講義やフォーラムに参加したことで、もしかすると新しい気づきから人生が変わるかもしれません。「DS・AIへの興味がちょっと湧いてきた」、でもいい。少しでも変わるきっかけをつかんでもらえればいいなと思っています。


本田 そして企業の方には「我が社はDS・AIでこれだけ面白い取り組みをしている」ということを、学生へ向けて熱く語っていただきたいですね。例えば、素材系メーカーの方などは「学生に注目してもらえない」と思われているようですが、決してそんなことはありません。本学の学生の多くは研究開発職を目指しているので、非常に高い関心を持っています。ぜひ、取り組みの新しさ、研究開発の面白さややりがいをアピールする場として使っていただきたいと思います。
本学は社会の課題解決を図っていけるような「共創型エキスパート人材」の育成を目指しています。これは大学だけでは進められず、企業の方との共同教育によって初めて実現できるものです。活力ある未来を創造できるリーダーの育成に、ぜひ力を貸していただきたいと思います。
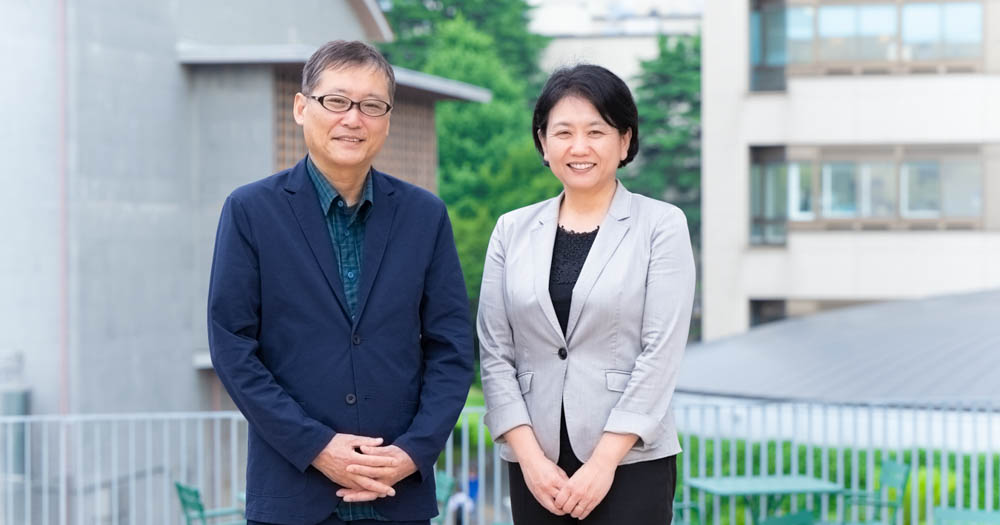
オフレコトーク
佐藤さん、本田さん、これまでの経歴は?
佐藤 証券系シンクタンクのSEとしてキャリアを始め、監査法人でシステムコンサルと監査を経験。新人研修で教える難しさと子育てで教育の重要性を痛感し、その後教育業界に転じました。でも実は、学生時代は公務員になるつもりだったんです。試験に受かり、本当にこの職で自分が納得できるか真剣に考えた末に「違う」と思い、新たな分野で就職活動を始めました。もしもあのままだったら今頃全く違う人生を歩んでいたことでしょう。
本田 前職はITベンダーで、顧客企業の課題を解決するためのソリューションの提供や、業務改善のコンサルティング業務に携わっていました。今は大学職員として、企業と本学学生との距離を縮める役割を担っていますが、「高度な人材を企業へ送り込む」という意味で、企業や社会をより良くしていくことに貢献できているのではないかと考えています。